| 2015年8月19日(日)曇り |
| 「野火」を読む |
先日、大岡昇平の「野火」を読了した。もう大昔の話になるが、この小説を一度手に取っ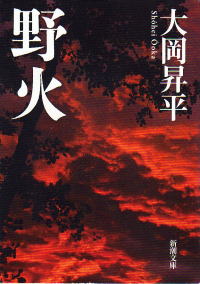 た記憶がある。そして多分、そのおどろおどろしい戦場の描写に怖くなったか、ストーリーに興味を失くしたか、途中で投げ出したのだろう。今回最後まで読み切って初めて、”野火”の持つ重い意味を、衝撃的に知らされたのだから・・・。 た記憶がある。そして多分、そのおどろおどろしい戦場の描写に怖くなったか、ストーリーに興味を失くしたか、途中で投げ出したのだろう。今回最後まで読み切って初めて、”野火”の持つ重い意味を、衝撃的に知らされたのだから・・・。
やはり、実に怖い小説だった。そしてこの小説が醸し出す「怖さ」の中身とは何なのだろうかと、ずっと考え続けてきた。それは少なくとも、この小説の大部分を占める戦争の酷さや風景としての戦場の悲惨さだけではない。(それもまた凄絶な文章の活写があるのだが)
「野火」の舞台は、太平洋戦争下のフィりピン・レイテ島の戦場である。敗残兵となった主人公は原野をさまよいながら極度の飢えに苦しみ、生の草を喰い、息絶えた兵士の顔に群がる山ビルを潰してその血を吸い、そして終には、遭遇した同僚から「猿の肉」と言って分け与えられた人肉まで口にする。
その同僚が食料の「猿」を探しに行った先で、主人公は人肉を漁る同僚と争いになり、銃で撃ち殺す。少なくともその争いは、主人公にとっては、ただ生き延びるために獣と化した人間の「狂気」への忌避と反抗であり、「正気」でありたいと思う自身の正当防衛だったと。そしてそのための殺人は、戦争という状況が起こした偶然であり、人間として正当化されるべき筋合いのものだと。
この小説で、戦場での描写はここで終わる。主人公の戦争体験の記憶が、ここでプツリと切れるからである。
終章の描写は、主人公が日本に帰還し精神病院に入って朧に記憶が戻るところから始まる。主人公の回想が、同僚を銃で撃ち、再び一人となって原野をさまよい、ついに”野火”を見つけて歩き出すところで、思わず読者は、その先を読み続けるのを躊躇し、しばし本を置いて瞑目することになるだろう。
読者は既に、主人公が極限の飢餓状態で人肉嗜食の誘惑に苛まれ、主人公が向かう野火の下には、そこに火を放った村人(!)がいることを、既読の文中で知らされているからである。
この小説の本髄と真の怖さは、ここにある。他の生き物とは画然と一線を引いてきた人間の尊厳と精神性に対する「揺らぎ」である。人間が、究極の苦難に置かれたとき、その「人間性」をどこまで保持できるかという問いかけを、この小説は戦争が孕む「狂気」の蓋然性によって炙り出しているのである。
主人公は”野火”(即ち「狂気」)に行き着く手前で敵に殴打され、そのまま記憶を失った。その「幸運」を主人公はこう叫んでこの小説は終わる。
”神に栄えあれ。” |
|
|
|