きっかけはおやじ山に籠っていた2014年9月、たまたま麓に下りて手にした新聞に宇沢弘文の死亡記事が載っていたことである。文化勲章受章者で、大学では数学を学んでいたが、河上肇の「貧乏物語」を読んで大きな感動を覚え、経済学に移ったこと、そして36歳で米国シカゴ大学の教授となり、彼の教え子の中にはノーベル経済学賞受賞者(ジョセフスティグリッツ教授)もいると書いてあった。この記事で印象に残ったことは、経済学を志すきっかけが河上肇の「貧乏物語」だったという点である。
また最近の新聞やテレビでは、パリ経済学校教授トマ・ピケティ氏の「21世紀の資本」論が先進諸国で大ベストセラーになっている、と報じていた。この本は18世紀まで遡る詳細なデータを駆使して格差の変化や所得の分配と経済成長について論じたもので、日本語版は今月(2014年12月)発売予定だという。
そして今年の秋の山暮らしも50日が過ぎて、そろそろおやじ山からの撤収の準備に取り掛かった10月28日、NHKラジオ朝いちばんの番組を聴いていると、「ビジネス展望」で経済評論家の内橋克人氏の「国は富めるも、民は貧し」と題した放送が流れた。このタイトルは河上肇の「貧乏物語」の冒頭部分に書かれた「国は著しく富めるも、民ははなはだしく貧し。げに驚くべきはこれら文明国における多数人の貧乏である」によるものであるという。
この短い番組の中で内橋氏は、格差社会を生む市場原理主義のもとで、価値が人間の命ではなく、富そのものに置かれていることを憂い日本社会の現代的貧困を問い続けた二人の経済学者が河上肇と宇沢弘文であると紹介してくれたのである。
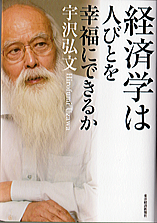 さらにまた、森林調査で福島県の山々を渡り歩いていた11月初旬(8日)、宿をとった湯岐温泉の朝のテレビ「あの人に会いたい」という番組で、今年の9月18日(2014年9月18日)に亡くなった宇沢弘文の映像を流していた。まさにテレビに目が釘づけになって「こんなド偉い学者がいたのか!」とすっかり感動してしまった。早速この人の書いた本と、この学者をして数学から経済学へと転向せしめた河上肇の「貧乏物語」は是非とも読まなければと思った次第である。
さらにまた、森林調査で福島県の山々を渡り歩いていた11月初旬(8日)、宿をとった湯岐温泉の朝のテレビ「あの人に会いたい」という番組で、今年の9月18日(2014年9月18日)に亡くなった宇沢弘文の映像を流していた。まさにテレビに目が釘づけになって「こんなド偉い学者がいたのか!」とすっかり感動してしまった。早速この人の書いた本と、この学者をして数学から経済学へと転向せしめた河上肇の「貧乏物語」は是非とも読まなければと思った次第である。つまり、世界の先進諸国では、とりわけ日本では金持ちと貧乏人の格差がどんどん開いている現状で、その原因はどこにあって、何をどう解決したら良いのか、遅まきながら俺も考え始めた訳である。
折しも巷ではアベノミクスの評価がにぎにぎしく論じられていて、現安倍政権が掲げる成長戦略の要諦が『金の流れを、お金持ちから中間層へ、大企業から中小零細へ、中央から地方へという、いわゆるトリクルダウン(滴り効果)』という政治手法らしいが、俺にはいまださっぱり景気回復の実感が掴めず、如何にもトリクルダウンとは金持ち優遇の眉唾に思えて大いに疑問だったからである。
***********************************************
河上肇「貧乏物語」について

福島の山から帰って、早速インターネットのAmazonで「貧乏物語」(岩波文庫)と宇沢弘文著「経済学は人びとを幸福にできるか」(東洋経済新報社)を申し込んだ。貧乏物語は直ぐ宅配されたが「経済学は・・・」は弔問需要が多かったせいか、かなり遅れて送られてきた。
それで取り敢えずは「貧乏物語」をバッグに入れて、宮城・岩手の森林調査の仕事に出掛けた。旅先での空き時間にじっくり読もうと思ったからである。
「貧乏物語」は大正5年9月から12月まで「大阪朝日新聞」に連載された文章をそのまま一冊子としてまとめた本である。その「序」に著者河上肇は次のように書いている。
『ラスキンの有名なる句にThere is no wealth, but life(富何者ぞただ生活あるのみ)ということがあるが、富なるものは道を聞くという人生唯一の目的を達成するための手段としてのみ意義あるに過ぎない。しかして余が人類社会より貧乏を退治せんことを希望するも、ただその貧乏なるものがかくのごとく人の道を聞くの妨げとなるがためのみである。』
本書は上編・中編・下編の三編より構成されている。上編は「今日の社会が貧乏という大病に冒されつつあることを明らかにする」こと。そして中編で「大病の根本原因が那辺(なへん)にあるかを明らかにし」、下編は「貧乏根治策に入るの段階たらしむるにある」と著者は書いている。
驚くなかれ、今世界的なベストセラーとなっているトマ・ピケティ氏の「21世紀の資本」論よりもおよそ100年も前に、既に河上は本書の上編で英・米・仏・独といった先進国の貧富の格差をデータやグラフで示し(もちろんトマ・ピケティとは手法も精度も違うだろうが)次のように書いている。 「最富者は全人口のわずか百分の二に相当するだけのものたるにかかわらず、その所有に属せる富は、英国にあっては全国の富の約七割二分、フランスにあってはその六割強、ドイツにあっては五割九分、米国にあっては五割七分に相当しているのである。」
さて中編であるが、この「物語」の真骨頂といえる部分かもしれない。フォルソムの『昆虫学』に出てくる「葉切り蟻」の話あり、ピテクァントロプスやエアントロプスの遺骨発掘から人類の道具の発明に至る人類学と経済史の話しがあり、マルサスの「人口論」に触れと、河上肇の博覧強記と知の横溢に唖然としつつ読み進めることになる。そして河上はこう言っているのである。
「今日社会の多数の人々が、充分に生活の必要品を得ることができなくて困っているのは・・・分配のしかたが悪いというがためではなくて、実は初めから生活の必要品は充分に生産されておらぬのである。」何故なら「需要というのは、単に要求と同じではなく・・・一定の要求に資力が伴うて来て、初めてそれが需要となり・・・今日の社会では、生活必需品に対する需要よりも、奢侈ぜいたく品にたいする需要のほうが、いつでもはるかに強大優勢である。」(大正5年!に河上はこう論破したのである)
そして肝心の下編である。河上は先ずアダム・スミスの「国富論」を、「彼は各個人が各自の利益を追求することを是認し、これになんらの束縛を加えず、自然のままにこれを放任することによりて、始めて社会の繁栄を期し、最大多数の幸福を実現するを得べし」とした利己心是認の思想だと批判した。そして氏は、「現代経済組織の下における利己心の束縛なき活動が・・・悲しむべき不健全なる状態を醸成し、一方には大廈高楼(たいかこうろう)にあって黄金の杯に葡萄の美酒を盛る者あるに、他方には襤褸(らんる)をまとうて門前に食を乞う者あるがごとき」だと嘆いているのである。
結局は著者河上が示した貧乏根絶の方策は、富者による奢侈の廃止と社会政策、社会主義の三策だが、「私の重きを置くところは飽くまで、富者の奢侈廃止である。」と書いている。
この本は一度絶版となり、終戦直後の1947年9月(昭和22年)に岩波書店から第1刷が再発行された。現版は第73刷だが、昭和47年の第40刷時点で40万冊以上の発売部数になったというから、当初の大阪朝日新聞の購読者はもとより、本書を含めて厖大な読者を得たことになる。
本書の巻末にはかの大内兵衛が初版時に書いた「解題」と、1972年(昭和47年)に書いた「追記」の以下の文が載っている。
「・・・(貧乏物語の)材料はイギリス伝来であり、問題のとらえ方は古典的であって新味はなく、その解決に至ってはさらに平凡であるが、それでも、ともかくも、一個の日本人の頭で咀嚼した上で、一個の切実な問題として問題提起がなされているという点において、そしてその人道的立場が問題とピッタリと合致している点において、みごとな完成品である」
「彼(河上肇)が提示した問題の方はこの半世紀のうちにおいて、あのときと比して何倍何十倍も大きくなって諸君の前にその姿をあらわしている。(昭和47年時点でさえ!)・・・『貧乏物語』の問題は、河上が問いかけただけでは解決しなかったけれど、「人類はつねに、自分の解決できる課題だけを提出する」(マルクス)。しかし諸君!正しく提出された問題なら、正しく解くのは諸君の義務ではないか。」
何と感動的な檄文であろうか!この大内兵衛の言葉を胸に刻んで、アベノミクスで走る今の日本経済を心底憂慮する次第である。
(2014年12月3日 記 )